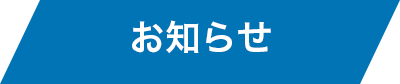[ 健太郎のオヌヌメ Voice Sound! in Youtube Vol,29 ]
2025-10-13こんにちは!ミュージックスクールドリーム音楽講師の木村健太郎です
今回のピックアップアーティストはこちら▼
なごり雪/イルカ Covered by satsuki.
こちらの名曲「なごり雪」(作詞・作曲:伊勢正三/歌:イルカ)は、日本のフォークソング史において非常に重要な位置を占める作品です。
1975年から色褪せることなく歌い継がれている名曲はコレからのシーズンに向けてベストマッチしますね
とてみ丁寧に力強くうたっておりsatsukiさんの個性が出てきていると思います
さて、今回から歌唱曲についてのポイントを勝手ながら音楽的・歌詞的・文化的な観点からまとめてみました!
なごり雪/イルカ
| 項目 | ポイント |
| メロディ | シンプルながら哀愁を帯びた旋律。サビにかけての転調が美しく、季節の移ろいを感じさせる構成。 |
| 歌詞 | 日常の別れを詩的に描写しながら、心情の奥行きを見事に表現。日本語の美しさが際立つ。 |
| 歌唱表現(イルカ) | 柔らかく透明感のある声質が楽曲の情景とマッチ。少し控えめな歌唱が「去りゆく季節」の儚さを引き立てている。 |
| アレンジ | シンプルなフォークサウンドだが、アコースティックギターとストリングスの調和が心地よい。 |
| 文化的影響力 | 卒業・別れの季節の定番曲として、世代を超えて歌い継がれている。日本の「春の情景ソング」の代表格。 |
▼歌詞の特徴と分析
『汽車を待つ君の横で 僕は時計を気にしてる 季節外れの雪が降ってる』
冒頭からすぐに“時間”と“季節”の対比が描かれます。
「季節外れの雪」は、時間のズレ=心のすれ違いを象徴しており、わずか数行で別れの情景と感情の温度差を伝えています。
『君が去ったホームに残り 落ちては溶ける雪を見ていた』
このラストラインに向かって、主人公の内面が静かに収束していく構成。
“雪”が「思い出」「余韻」「なごり」と重なり、まさにタイトルの「なごり雪(=去り際に残る余情)」が完成します。
▼ 歌唱面でのポイント(イルカver)
イルカの声は「澄んだ少年のような少女声」。
感情を過剰に出さず、淡々と語るように歌うことで、“時間が止まった駅のホーム”という情景に静けさと温もりを与えています。
この「抑制された表現」がフォークソングの精神を体現しており、結果的に多くのリスナーに「自分の記憶」を重ねさせる余白を生んでいます。
▼ なごり雪 ― 歌唱ポイント3選 ―
① 息の流れで“情景”を描く(ブレスコントロール)
この曲は力で歌うよりも「空気の流れ」で情感を出すタイプ。
たとえば冒頭の「汽車を待つ君の横で〜」
のフレーズは、息を吐きながら語るように歌うのがコツです。
- 声を「出す」より「流す」
- 息の粒子で“白い雪が舞う”ようなイメージを描く
- 「時計を気にしてる」の語尾を少し抜いて、“遠くを見つめるように”
→ ブレスを多めに取りながら「ウィスパーボイス気味に」、淡く・浮遊感のある声で進めると世界観が生まれます。
② 抑揚ではなく“温度差”で感情を出す
この曲の感動ポイントは「大きな盛り上がり」ではなく、「温度の変化」。
つまり、感情の上下よりも“距離感”で切なさを表現します。
- 前半:「少し距離を置いたナレーションのように」
- 後半(特に“君が去ったホームに残り…”以降):
→ 声にわずかな温もりを乗せ、心の内を語るようにトーンアップ
→声量ではなく、「声の温度」で聴かせる。
“体温1度分の変化”を意識すると、聴き手の心を動かせます。
③ 語尾を「消えるように」終わらせる(残響の美学)
“なごり雪”の世界では、語尾が残る時間が「余韻」になります。
だからこそ、言葉を言い切らない勇気が大切です。
例:
「…僕は時計を気にしてる」
→ 「る」を切らずに、息ごと“雪に溶けるように”消える。
「…落ちては溶ける雪を見ていた」
→ 「た」を止めずに、息でフェードアウト。
→
声の終わりが“情景の終わり”。
マイク録音の場合は特に、語尾の空気音(ブレス)まで表現の一部にしましょう。
まとめ
| ポイント | 意識すること | 効果 |
| ① 息の流れ | 空気で語るように歌う | 柔らかく温かい印象に |
| ② 声の温度差 | 声量より「心の距離」で表現 | 切なさ・余情が伝わる |
| ③ 語尾の消え方 | 息とともにフェードアウト | “なごり”の余韻が残る |
いかがだったでしょうか?これからの季節に向けてカラオケで高得点を狙ってみてください!