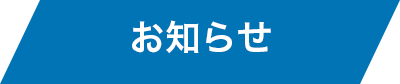MSD声優講師の小言『こんな感情を出したいから』
2025-07-14感情は「出す」ものではなく「生きる」もの。
表面的な「型」が、あなたの芝居を壊す。
演じる上で、「こんな感情を出したいから、どうやるか、どうアクションするかを決めてしまう」。この考え方が、あなたの芝居をダメにしてしまうことをご存じですか?
感情表現の「型」が芝居を損なう理由
多くの人が、ある感情を表現しようとする際に、無意識のうちに
「悲しいから泣く」
「怒っているから大声を出す」
「嬉しいから笑う」
といった、典型的な表現パターンや行動を先に考えてしまいがちです。あなたも、こういった経験はありませんか?
このアプローチがなぜ芝居を損なうのか、その理由は以下の通りです。
上辺だけの表現になる
感情を「型」にはめ込もうとすると、演じる側は「泣こう」「怒鳴ろう」という意識が先行し、感情の奥底にある複雑さや真実を見失います。
結果として、表面的で薄っぺらい、あるいは過剰な演技になりがちです。
観客はすぐに「作られた感情」だと見抜いてしまいます。
キャラクターの真実から離れる
人は皆、同じ感情でも、その時々の状況や性格、過去の経験によって表現の仕方が異なります。
例えば、深い悲しみを抱えていても、静かに涙を流す人もいれば、怒りに転じる人もいますよね。
あらかじめ「こう表現する」と決めてしまうと、そのキャラクター固有の真実味のある反応を見逃し、個性のない画一的な芝居になってしまいます。
内側の衝動が生まれない
真に心に響く演技は、感情が内側から湧き上がり、それが自然な身体の反応や声の変化として現れるときに生まれます。
しかし、「こうやろう」と先に決めてしまうと、この内側からの衝動が生まれる余地がなくなってしまいます。
頭でコントロールしようとすることで、感情が滞り、自由な表現が阻害されるのです。
感情を「出す」のではなく「生きる」こと
では、どうすれば良いのでしょうか。この言葉が指し示す本質的なアプローチは、感情を「出す」のではなく、「その感情をキャラクターとして生きる」ことにあります。
感情の「核」を深く探求する
まず、セリフや状況の裏にあるキャラクターの感情を、頭で考えるだけでなく、身体全体で感じ、その感情がどこから来ているのかを深く掘り下げます。
「この悲しみは、何に対するものなのか?」
「この怒りの根源は何なのか?」
といった問いを繰り返し、感情の源流に触れることを目指します。
身体と心を解放し、受け入れる
感情を感じ尽くしたら、「こう表現しよう」という意図を一度手放し、身体や声がその感情に対してどう反応したいか、自然に耳を傾けます。不必要な力みを抜き、感情が自然に声のトーン、表情、ジェスチャーとして現れるのを許容します。
それは、必ずしも「泣く」という行動になるとは限りませんよ?
内側から湧き上がる衝動に身を委ねる
感情が十分に深く感じられ、身体が解放されたとき、内側から自然な「衝動」が生まれます。
その衝動に身を委ね、現れるがままに任せることで、最も真実味があり、観客の心に深く訴えかける演技が生まれます。
このアプローチは、表面的なテクニックに頼るのではなく、感情の真実に触れ、それを自分という器を通して自然に顕現させることを目指します。
それこそが、観る人を魅了し、心に残る芝居を創り出すための、俳優や声優にとって最も大切な心構えです。
普段は感情を出せるのに、舞台や台本で出せない理由
そもそも、普段の生活では自然に感情を表現できるのに、いざ台本や舞台に立つと感情が出せなくなるのには、いくつかの明確な理由があります。これは、俳優や声優、パフォーマーが誰もが一度は直面する共通の悩みと言えるでしょう。
その主な理由を、3つの側面から見ていきましょう。
心理的な理由:プレッシャーと自己意識
普段の生活で感情が自然に出るのは、多くの場合、何の「評価」も「プレッシャー」もないからです。
しかし、台本や舞台という環境では、無意識のうちに以下のような心理状態に陥りがちです。
失敗への恐れ: 「間違えてはいけない」「うまくやらなければ」というプレッシャーが、感情を身体から切り離し、頭だけで演技をしようとさせてしまいます。
過剰な自己意識: 「どう見られているだろう」「変な顔をしていないか」という意識が強くなり、自分を客観視しすぎてしまいます。
その結果、感情が内側で固まってしまい、外に流れ出なくなります。
「演じる」ことへの意識のズレ: 普段の感情は自然な心の動きから湧き出るものですが、台本上の感情は「作らなければ」「出さなければ」という意識になりがちです。
この意識が、かえって不自然で嘘っぽい表現を生んでしまうのです。
技術・アプローチの理由:感情の「型」にはめる癖
感情表現の経験が少ないうちは、感情を「こう表現するものだ」という型にはめようとしてしまうことがあります。
感情のストック不足: 普段の生活で感じる感情は非常に細かく複雑です。しかし、いざ演技となると、「悲しい」=「泣く」、「嬉しい」=「笑う」といった単純なパターンに頼りがちです。
その結果、キャラクターの奥深い感情を捉えきれず、表面的な演技になってしまいます。
「行動ありき」の思考: 以前お伝えしたように、「こんな感情を出したいから、どうやるか」と、先にアクションやテクニックを決めてしまうことが、感情の自然な流れを止めてしまいます。内側から湧き上がる衝動を待つのではなく、外側の形を先に作ろうとすることが、真実味のある感情表現を妨げます。
環境的な理由:非日常の空間
慣れない場所での緊張は、心身に影響を与えます。
慣れない場所での緊張: 舞台やスタジオ、カメラの前といった非日常的な空間にいること自体が、心身に緊張をもたらします。
この緊張は、声や身体を固くし、感情が自由に流れるのを妨げます。
相手との関係性の違い: 普段の感情は目の前の人との関係性ややり取りの中で生まれますが、台本上の感情は、設定された架空の関係性の中で生み出さなければなりません。
この違いに戸惑い、感情が湧きにくいと感じることがあるんです。
これらの理由を乗り越えるためには、感情を「出そう」とするのではなく、「そこにある」と信じること。
そして、心と身体の繋がりを再び取り戻すトレーニングが重要となります。
ミュージックスクールドリームの声優講座は、まさにお話ししてきた「感情を『出す』のではなく『生きる』」という視点からレッスンを行っています。
単に声のテクニックを教えるだけでなく、あなたが心から役の感情を表現できる声優になるためのアプローチを重視しています。
ミュージックスクールドリームの声優講座では無料体験レッスンをしています。
ご興味がある方は お問い合わせください☆彡
※当日のレッスンにお越しになられる際には動きやすい服装と蓋つきの飲み物をご用意ください。必要であれば筆記用具等も🎵